- 履歴書に記載する学歴の書き方
- 注意すべき職歴の書き方
- 履歴書の書き方に悩んだ時におすすめの転職エージェント
転職活動に使用する履歴書を作成する際に、「学歴はどこから書いたら良いのだろう」と疑問に思った方も多いのではないでしょうか。
一般的に、転職活動を行う際には学歴や職歴、資格などを記載した履歴書を準備します。
特に、転職活動が初めての人は、「中学校から書くと学歴が長くなってしまう」「学歴と職歴のバランスが気になる」などと悩んでしまう場合があります。
そこで本記事では、履歴書の書き方やさまざまなケース別に合わせた履歴書作成のルールについて、サンプルも含めて紹介します。
また、正しい学歴・職歴の書き方に悩んだ時のために、おすすめの転職エージェントも紹介しているため、ぜひ今後の転職活動の参考にしてください。
履歴書の書き方について不安な方や添削を希望する方は、マイナビエージェントの利用がおすすめです。履歴書・書類の添削はもちろんのこと、面接対策までサポートしてくれるため、面接に繋がりやすい意義のある履歴書を作成できます。

\応募書類の添削サポートも手厚い!/
転職の履歴書の学歴はどこから書けばいい?
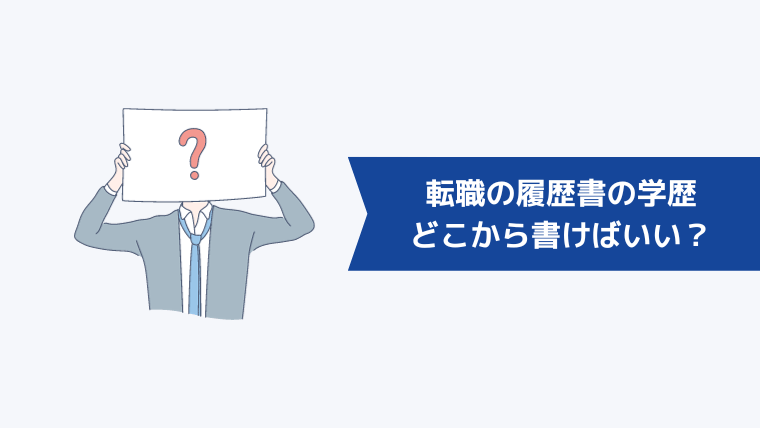
履歴書の学歴をどこから書くかについては、明確な決まりはありません。
そのため、応募先企業からの特別な指定がない限りは、「高校入学」から記載しておけば問題ないでしょう。
また、学校名については「〇〇高校」ではなく、「〇〇高等学校」のように正式名称で記載する必要があります。
学部や学科名がある場合も、省略せずに正しく記載しましょう。
履歴書には、職歴についても記載する必要があるため、「記入欄が足りなかった!」とならないように、書き始めには記入分のスペースを確保しておくことが重要です。
正式書類を正しく書けないと、業務に悪影響を及ぼす可能性もあると判断され、それだけで選考において不利になる場合もあります。
そのため、記入が終わった後は必ず、間違いがないか確認作業を忘れずに行いましょう。
転職の履歴書の学歴欄の書き方【基本ルールまとめ】
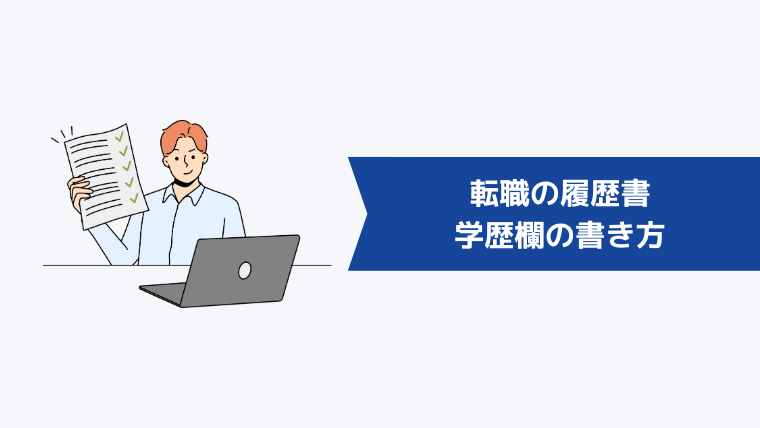
書類選考時に少しでも良い印象を残すために、履歴書の学歴欄の書き方のルールは押さえておきましょう。
- 1行目の中央には「学歴」と記載する
- 学校や学部・学科は正式名称で記載する
- 入学や卒業の学校名が同じでも「同上」と省略しない
- 入学年や卒業年などは和暦か西暦で統一する
- 浪人・留年はあえて書く必要なし
- 中退した場合には「中途退学」と記載しておく
履歴書の学歴欄は、応募者がそれまでどのような教育を受けてきたかを伝えるためのものです。
とはいえ、人事担当者や採用担当者は「高学歴であるか」「有名校出身であるか」などを気にしているのではなく、学校や学部などの選び方に注目しています。
多くの選択肢の中で、応募者がその進学先を選んだ理由や、その先にイメージしているキャリア設計に思いを馳せます。
そのため、自身の人柄や人生観、考え方を見てもらえるように、最低限の履歴書の記入ルールは押さえておきましょう。
転職の履歴書の学歴欄の記入例・サンプル
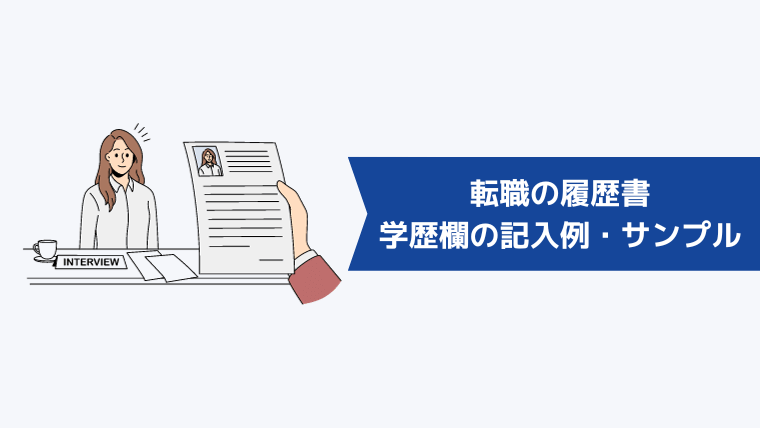
転職の際に利用する、履歴書の学歴の書き方について、下記でサンプルを紹介します。
| 年 | 月 | 学歴・職歴 |
| 学歴 | ||
| 20〇〇 | 4 | 東京都〇〇高等学校 入学 |
| 20〇〇 | 3 | 東京都〇〇高等学校 卒業 |
| 20〇〇 | 4 | 〇〇大学〇〇学部〇〇学科 入学 |
| 20〇〇 | 3 | 〇〇大学〇〇学部〇〇学科 卒業 |
学歴欄の1行目には「学歴」と中央に書き、その次の行から実際の学歴を記載します。
大学・短大・専門学校について、応募先の仕事で活かせる研究などに携わった場合には積極的に記入しても良いでしょう。
面接時に質問された場合には、自身のアピールの場にもなります。
また、自身の卒業年度がわからない場合には、以降で「年号早見表」を紹介していますので、ぜひ活用してみてください。
【ケース別】学歴欄の記入方法
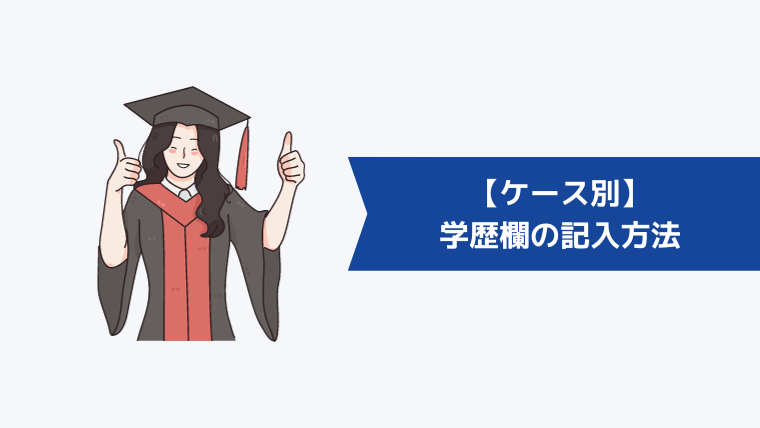
受けてきた教育や選んだ学校はそれぞれ異なるがゆえに、中には以下のような経験をされた方もいるでしょう。
- 中途退学の経験があるケース
- 転校・編入の経験があるケース
- 学部・学科変更の経験があるケース
- 休学・浪人・留年の経験があるケース
- 海外留学の経験があるケース
- 社会人を経験した後で学生に戻っているケース
- 学歴が書ききれないほどあるケース
下記で、それぞれのケースについて学歴欄の記入方法について紹介していきます。
中途退学の経験があるケース
長期の休学や中途退学の経験がある場合には、面接でも質問される可能性が高いため、あらかじめ履歴書に理由を記入しておく必要があります。
その場合には、上述したように「中途退学」と記載し、「家庭の事情により中途退学」などと簡潔に理由を記載しておきましょう。
| 年 | 月 | 学歴・職歴 |
| 学歴 | ||
| 20〇〇 | 4 | 東京都〇〇高等学校 入学 |
| 20〇〇 | 3 | 東京都〇〇高等学校 卒業 |
| 20〇〇 | 4 | 〇〇大学〇〇学部〇〇学科 入学 |
| 20〇〇 | 6 | 〇〇大学〇〇学部〇〇学科 中途退学(家庭の事情により) |
また、中途退学を卒業と偽ることは学歴詐称になってしまうため、嘘のないように、正確に書くことを意識してください。
転校・編入の経験があるケース
転校した場合には、転校前の学歴欄の1行下に、転校先の学校名と「転入学」を記載します。
また、大学や専門学校を変更した際には、「編入学」と記載します。
| 年 | 月 | 学歴・職歴 |
| 学歴 | ||
| 20〇〇 | 4 | 東京都〇〇高等学校 入学 |
| 20〇〇 | 8 | 東京都〇〇高等学校 転入学 |
| 20〇〇 | 3 | 東京都〇〇高等学校 卒業 |
| 20〇〇 | 4 | 〇〇大学〇〇学部〇〇学科 入学 |
| 20〇〇 | 6 | △△大学△△学部△△学科 編入学 |
| 20〇〇 | 3 | △△大学△△学部△△学科 卒業 |
転入学や編入学部分が抜けていると、人事担当や採用面接者に「なぜ抜けているのか」「単なるミスなのか」と考えさせてしまう可能性もあるため、転入学・編入学の部分は明示的に記載しましょう。
学部・学科変更の経験があるケース
学校は変更せずに、学部や学科のみを変更している場合には、入学の学歴欄の1行下に、改めて変更先の学校名と学部や学科を記載します。
| 年 | 月 | 学歴・職歴 |
| 学歴 | ||
| 20〇〇 | 4 | 東京都〇〇高等学校 入学 |
| 20〇〇 | 3 | 東京都〇〇高等学校 卒業 |
| 20〇〇 | 4 | 〇〇大学〇〇学部〇〇学科 入学 |
| 20〇〇 | 6 | 〇〇大学△△学部△△学科 編入学 |
| 20〇〇 | 3 | 〇〇大学△△学部△△学科 卒業 |
そして、1文字空けた横に「編入学」と記載してください。
また、高校で学科を変更した場合にも、書き方は同様となります。
休学・浪人・留年の経験があるケース
1、2年の浪人、留年であれば特にマイナスイメージを持たれる可能性も少ないため、履歴書への記入は不要です。
入学と卒業年度が正しく記載されていれば、その期間に浪人または留年があったことは、採用担当者に伝わります。
その一方で、休学に関しては、以下のように学歴欄へ記載する必要があります。
| 年 | 月 | 学歴・職歴 |
| 学歴 | ||
| 20〇〇 | 4 | 東京都〇〇高等学校 入学 |
| 20〇〇 | 3 | 東京都〇〇高等学校 卒業 |
| 20〇〇 | 4 | 〇〇大学〇〇学部〇〇学科 入学 |
| 20〇〇 | 6 | 〇〇大学〇〇学部〇〇学科 休学 |
| 1年間、家庭の事情により休学 | ||
| 20〇〇 | 3 | 〇〇大学〇〇学部〇〇学科 卒業 |
休学は、憶測などにより不信感を持たれないためにも、簡潔に理由を記載しておくと誤解を招かずに済みます。
また、怪我や病気などで休学していた場合には、直近数年間の出来事に限ってのみ、念のため業務に支障が出ない旨も伝えておくと採用担当者は安心します。
海外留学の経験があるケース
長期の海外留学は、選考に有利に働くこともあるため、積極的に記載しましょう。
| 年 | 月 | 学歴・職歴 |
| 学歴 | ||
| 20〇〇 | 4 | 東京都〇〇高等学校 入学 |
| 20〇〇 | 3 | 東京都〇〇高等学校 卒業 |
| 20〇〇 | 4 | 〇〇大学〇〇学部〇〇学科 入学 |
| 2年次に1年間アメリカ〇〇大学〇〇学部〇〇学科へ留学 | ||
| 20〇〇 | 3 | 〇〇大学〇〇学部〇〇学科 卒業 |
上記のように、大学の入学と卒業の間に1行で、期間と学校名(学部名・学科名)をそれぞれ記載するのが一般的です。
学歴欄に記載する留学期間の目安としては、1年以上が妥当です。
短期留学やホームステイの場合には、留学としては扱われません。
そのためアピールしたい場合には、自己PR欄や志望動機欄を利用すると良いでしょう。
社会人を経験した後で学生に戻っているケース
大学を卒業して、一旦就職したのちに再度大学や専門学校などに入学した場合や、大学卒業後に社会人経験を経て大学院に入学した場合には、学歴欄にはそのまま記載しましょう。
| 年 | 月 | 学歴・職歴 |
| 学歴 | ||
| 2010 | 4 | 東京都〇〇高等学校 入学 |
| 2012 | 3 | 東京都〇〇高等学校 卒業 |
| 2012 | 4 | 〇〇大学〇〇学部〇〇学科 入学 |
| 2016 | 3 | 〇〇大学〇〇学部〇〇学科 卒業 |
| 2020 | 4 | 〇〇大学〇〇学部〇〇学科 入学 |
| 職歴 | ||
| 2016 | 4 | 株式会社〇〇〇〇 入社 |
| 2020 | 3 | 一身上の都合により退職 |
| 以上 |
上記のように、特に明記せずとも、時期を見れば採用担当者は判断できるため、学歴欄へ詳細を記入する必要はありません。
面接時に質問された際に、理由や背景について納得してもらえるように説明できれば、自己PRとして強みにもなり得るでしょう。
学歴が書ききれないほどあるケース
何度も転校や中退をしていると、学歴に記載する内容が多くなる場合があります。
その場合には、学歴や職歴が履歴書に入りきれないからといって省略するのはやめましょう。
省略することで空白期間が生まれてしまうため、採用担当者は学歴に不信感を抱いてしまう可能性があります。
そのため、まずは学歴を優先的に、時系列に沿って記載します。
どうしても学歴が多くなって記入欄が不足する場合には、最終学歴の1つ前の卒業から記載すると良いでしょう。
転職の履歴書は学歴だけでなく職歴の書き方にも要注意!
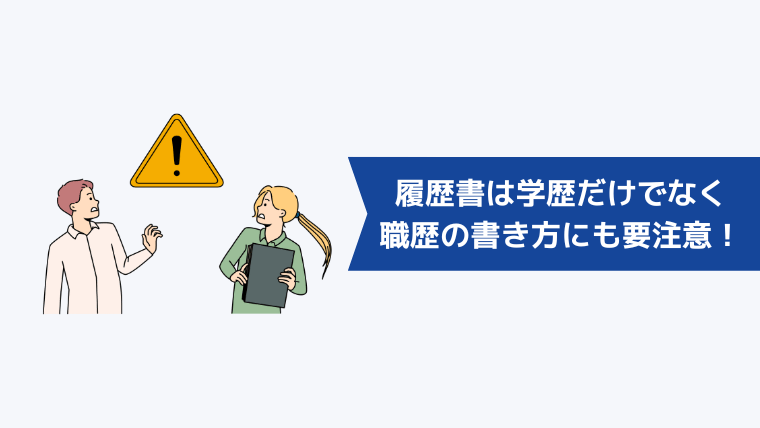
転職の際に使用する履歴書は、学歴だけでなく職歴の書き方にも注意が必要です。
- 職歴欄の書き方の基本ルール
- 職歴欄の記入例・サンプル
- 職歴が書ききれないときの対処法
以降で詳しく解説していきますので、ぜひ最後まで確認してみてください。
職歴欄の書き方の基本ルール
職歴の書き方も、基本的には学歴の記載ルールと同じです。
- 職歴欄と学歴欄の間は1行空ける
- 職歴を書き始める最初の行の中央に「職歴」と書く
- 入学年や卒業年などは和暦か西暦で統一する
- 社名や医療機関は正式名称で記載
- 所属部署・雇用形態を明記する
- 会社名の横か次の行に業種や従業員数、簡単な職務内容について記載
- 短期間しか勤務していない場合も記載する
- 退職した場合は「一身上の都合により退職」と記載
- 現職の企業の退職日が決まっている場合には「令和◯年 ◯月 株式会社〇〇〇〇 退職予定」と記載
- 在職中も含み最終職歴の下には「現在に至る」と記載
- 最終行の右下に「以上」と書く
退職理由は「一身上の理由により退職・退社」と記載するのが一般的で、具体的な理由は必要ありません。
また、学生時代のアルバイトは職歴には含まないため、大学や専門学校などを卒業した後の仕事から職歴を記載しましょう。
社会人になった後にアルバイトの経験がある場合には、応募先企業での職種に活かせるような業務であれば有利に働く可能性があるため、数ヶ月程度の短期間のアルバイト以外は記載して問題ありません。
職歴欄の記入例・サンプル
職歴欄の記入例として、サンプルを紹介します。
| 職歴 | ||
| 20〇〇 | 4 | 株式会社〇〇〇〇 入社 |
| 広告代理店業 従業員数588名 | ||
| 東京支社 第1営業部 営業1課 | ||
| 広告代理店営業担当として新規開拓営業を行う | ||
| 20〇〇 | 3 | 一身上の都合により退職 |
| 以上 |
採用担当者は、過去の職歴欄から、「自社で活躍できる人材か」「自社の風土に合った人材か」を見極めています。
前職の仕事内容や、退職に至った経緯などを職歴欄から読み取り、採用した場合にはどのポジションで受け入れるか、どのような業務を任せるかをイメージするのです。
そのため、書類選考を有利に進めるためにも、1行で目を惹くような内容を記載できると良いでしょう。
職歴が書ききれないときの対処法
何度も転職している場合などには、余白がなくなり、学歴・職歴欄内に全てを記載しきれない場合もあるでしょう。
その場合に、職歴を省略してしまうのは望ましくありません。
省略して余白期間が生まれてしまうと、採用担当者が職歴に不信感を抱く可能性があるのです。
職歴は、下記のように「入社」「退職」や「現在に至る」「以上」などを同じ行にまとめて簡略化できます。
| 年 | 月 | 職歴 |
| 20〇〇 | 4 | 株式会社〇〇〇〇 入社(20〇〇年◯月 退職) |
| 20〇〇 | 6 | 株式会社〇〇〇〇 入社(20〇〇年◯月 退職予定) |
| 現在に至る | ||
| 以上 |
また、「現在に至る」は在職中の場合のみ使用し、退職して無職の状態の際には使用しないため、注意しておきましょう。
履歴書の学歴欄の記入に役立つ年号早見表【計算式】
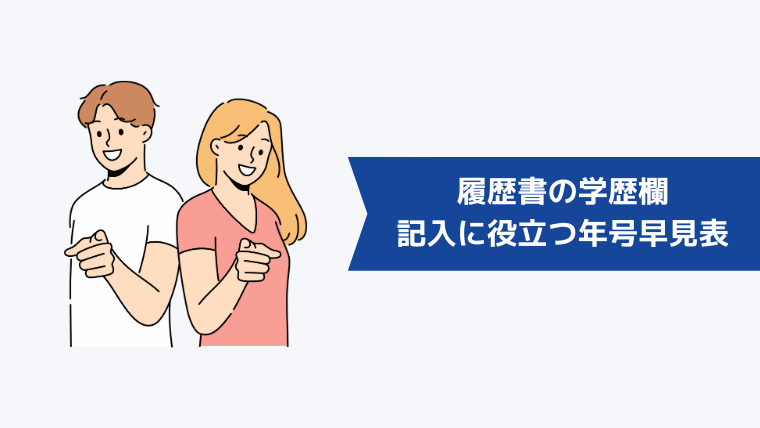
履歴書を記載する上で、学校の入学・卒業年の記載は必須であり、間違ってはならない項目の1つです。
以降に、卒業年度についてまとめていますので、履歴書を記載する際にはぜひ参考にしてみてください。
1965年~1974年生まれの早見表
| 生まれ年 | 中学卒業 (高校入学) | 高校卒業 (大学入学) | 短大卒業 | 大学卒業 |
| 昭和40年生 (1965年) | 昭和56年 (1981年) | 昭和59年 (1984年) | 昭和61年 (1986年) | 昭和63年 (1988年) |
| 昭和41年生 (1966年) | 昭和57年 (1982年) | 昭和60年 (1985年) | 昭和62年 (1987年) | 平成元年 (1989年) |
| 昭和42年生 (1967年) | 昭和58年 (1983年) | 昭和61年 (1986年) | 昭和63年 (1988年) | 平成2年 (1990年) |
| 昭和43年生 (1968年) | 昭和59年 (1984年) | 昭和62年 (1987年) | 平成元年 (1989年) | 平成3年 (1991年) |
| 昭和44年生 (1969年) | 昭和60年 (1985年) | 昭和63年 (1988年) | 平成2年 (1990年) | 平成4年 (1992年) |
| 昭和45年生 (1970年) | 昭和61年 (1986年) | 平成元年 (1989年) | 平成3年 (1991年) | 平成5年 (1993年) |
| 昭和46年生 (1971年) | 昭和62年 (1987年) | 平成2年 (1990年) | 平成4年 (1992年) | 平成6年 (1994年) |
| 昭和47年生 (1972年) | 昭和63年 (1988年) | 平成3年 (1991年) | 平成5年 (1993年) | 平成7年 (1995年) |
| 昭和48年生 (1973年) | 平成元年 (1989年) | 平成4年 (1992年) | 平成6年 (1994年) | 平成8年 (1996年) |
| 昭和49年生 (1974年) | 平成2年 (1990年) | 平成5年 (1993年) | 平成7年 (1995年) | 平成9年 (1997年) |
1975年~1984年生まれの早見表
| 生まれ年 | 中学卒業 (高校入学) | 高校卒業 (大学入学) | 短大卒業 | 大学卒業 |
| 昭和50年生 (1975年) | 平成3年 (1991年) | 平成6年 (1994年) | 平成8年 (1996年) | 平成10年 (1998年) |
| 昭和51年生 (1976年) | 平成4年 (1992年) | 平成7年 (1995年) | 平成9年 (1997年) | 平成11年 (1999年) |
| 昭和52年生 (1977年) | 平成5年 (1993年) | 平成8年 (1996年) | 平成10年 (1998年) | 平成12年 (2000年) |
| 昭和53年生 (1978年) | 平成6年 (1994年) | 平成9年 (1997年) | 平成11年 (1999年) | 平成13年 (2001年) |
| 昭和54年生 (1979年) | 平成7年 (1995年) | 平成10年 (1998年) | 平成12年 (2000年) | 平成14年 (2002年) |
| 昭和55年生 (1980年) | 平成8年 (1996年) | 平成11年 (1999年) | 平成13年 (2001年) | 平成15年 (2003年) |
| 昭和56年生 (1981年) | 平成9年 (1997年) | 平成12年 (2000年) | 平成14年 (2002年) | 平成16年 (2004年) |
| 昭和57年生 (1982年) | 平成10年 (1998年) | 平成13年 (2001年) | 平成15年 (2003年) | 平成17年 (2005年) |
| 昭和58年生 (1983年) | 平成11年 (1999年) | 平成14年 (2002年) | 平成16年 (2004年) | 平成18年 (2006年) |
| 昭和59年生 (1984年) | 平成12年 (2000年) | 平成15年 (2003年) | 平成17年 (2005年) | 平成19年 (2007年) |
1985年~1994年生まれの早見表
| 生まれ年 | 中学卒業 (高校入学) | 高校卒業 (大学入学) | 短大卒業 | 大学卒業 |
| 昭和60年生 (1985年) | 平成13年 (2001年) | 平成16年 (2004年) | 平成18年 (2006年) | 平成20年 (2008年) |
| 昭和61年生 (1986年) | 平成14年 (2002年) | 平成17年 (2005年) | 平成19年 (2007年) | 平成21年 (2009年) |
| 昭和62年生 (1987年) | 平成15年 (2003年) | 平成18年 (2006年) | 平成20年 (2008年) | 平成22年 (2010年) |
| 昭和63年生 (1988年) | 平成16年 (2004年) | 平成19年 (2007年) | 平成21年 (2009年) | 平成23年 (2011年) |
| 平成元年生 (1989年) | 平成17年 (2005年) | 平成20年 (2008年) | 平成22年 (2010年) | 平成24年 (2012年) |
| 平成2年生 (1990年) | 平成18年 (2006年) | 平成21年 (2009年) | 平成23年 (2011年) | 平成25年 (2013年) |
| 平成3年生 (1991年) | 平成19年 (2007年) | 平成22年 (2010年) | 平成24年 (2012年) | 平成26年 (2014年) |
| 平成4年生 (1992年) | 平成20年 (2008年) | 平成23年 (2011年) | 平成25年 (2013年) | 平成27年 (2015年) |
| 平成5年生 (1993年) | 平成21年 (2009年) | 平成24年 (2012年) | 平成26年 (2014年) | 平成28年 (2016年) |
| 平成6年生 (1994年) | 平成22年 (2010年) | 平成25年 (2013年) | 平成27年 (2015年) | 平成29年 (2017年) |
1995年~2004年生まれの早見表
| 生まれ年 | 中学卒業 (高校入学) | 高校卒業 (大学入学) | 短大卒業 | 大学卒業 |
| 平成7年生 (1995年) | 平成23年 (2011年) | 平成26年 (2014年) | 平成28年 (2016年) | 平成30年 (2018年) |
| 平成8年生 (1996年) | 平成24年 (2012年) | 平成27年 (2015年) | 平成29年 (2017年) | 平成31年 (2019年) |
| 平成9年生 (1997年) | 平成25年 (2013年) | 平成28年 (2016年) | 平成30年 (2018年) | 令和2年 (2020年) |
| 平成10年生 (1998年) | 平成26年 (2014年) | 平成29年 (2017年) | 平成31年 (2019年) | 令和3年 (2021年) |
| 平成11年生 (1999年) | 平成27年 (2015年) | 平成30年 (2018年) | 令和2年 (2020年) | 令和4年 (2022年) |
| 平成12年生 (2000年) | 平成28年 (2016年) | 平成31年 (2019年) | 令和3年 (2021年) | 令和5年 (2023年) |
| 平成13年生 (2001年) | 平成29年 (2017年) | 令和2年 (2020年) | 令和4年 (2022年) | 令和6年 (2024年) |
| 平成14年生 (2002年) | 平成30年 (2018年) | 令和3年 (2021年) | 令和5年 (2023年) | 令和7年 (2025年) |
| 平成15年生 (2003年) | 平成31年 (2019年) | 令和4年 (2022年) | 令和6年 (2024年) | 令和8年 (2026年) |
| 平成16年生 (2004年) | 令和2年 (2020年) | 令和5年 (2023年) | 令和7年 (2025年) | 令和9年 (2027年) |
初めの1枚を間違えてしまうと、その後の履歴書も間違ったまま記載する可能性が高いため、初めの1枚は必ず入念に確認しましょう。
転職の履歴書で学歴・職歴欄の書き方に悩む人からよくある質問
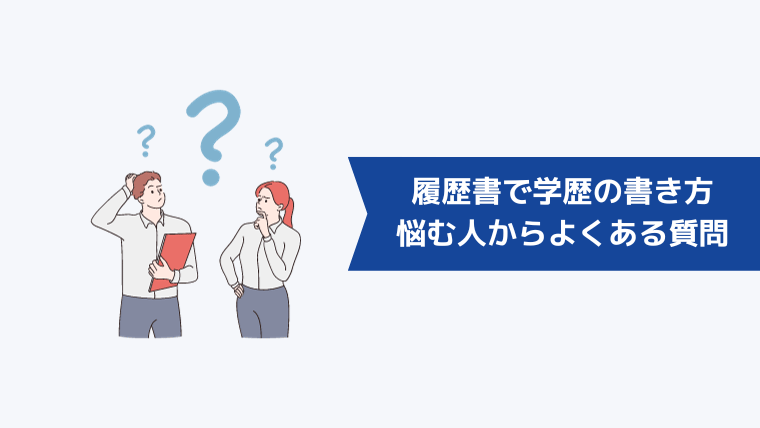
履歴書に記載する際に、学歴欄や職歴欄の書き方に迷う人からの質問を紹介していきます。
- 履歴書の職歴はどこまで記入する?
- 社会人経験が浅い場合は学歴をどこから書けばいい?
- 大学院卒業の場合は学歴をどこから書けばいい?
- 職業訓練校や民間スクールでの学びはどこに書けばいい?
当てはまる項目がある方は、ぜひ参考にしてみてください。
履歴書の職歴はどこまで記入する?
履歴書に記載すべきものは「全ての職歴」です。
また、入社・退社年も正確に記載しましょう。
所属部署や雇用形態についても、人事担当者や採用面接官に事前にこれまでの業務内容を正しく伝えられるため、記載しておくのが望ましいです。
応募先企業に合わせて自身のアピールポイントも変えるなど、書類選考を通過する履歴書を作成できるように工夫していきましょう。
社会人経験が浅い場合は学歴をどこから書けばいい?
第2新卒や転職経験がない、あるいは転職経験が少ない場合など、社会人経験が少ない方もいるでしょう。
その場合に、履歴書に記載する職歴も少ないため、余白ができてしまう可能性があります。
できるだけ余白を埋めたい場合には、学歴は「高等学校卒業」からではなく「中学校卒業」から記載しても問題ありません。
あくまで、履歴書全体の余白の割合などから、見やすさを意識して作成すると良いでしょう。
第二新卒の学歴・職歴の書き方のポイントについて「第二新卒の履歴書の書き方|通過率を高める方法や採用担当者の印象に残るポイントを解説!」をぜひ参考にしてください。
大学院卒業の場合は学歴をどこから書けばいい?
大学院卒業の方は、学歴が長くなってしまいますが、その場合でも「高等学校卒業」から記載して問題ありません。
また、大学院は修士課程と博士課程があるため、それぞれの入学年次や修了年次を正確に記載する必要があります。
上述したように、最終学歴が大学院の場合は「卒業」ではなく「修了」と記載する必要があるため、間違いがないように注意しましょう。
在学中の方は、「修了見込み」の記載も忘れずにしましょう。
職業訓練校や民間スクールでの学びはどこに書けばいい?
結論から言うと、職業訓練校は「職歴欄」、民間スクールでの学びは「資格・特技欄」に記載します。
職業訓練校は、職業能力開発促進法において規定された厚生労働省管轄の公共職業訓練施設であるため、学歴にはならないのです。
また、以下のように、管轄する省庁によって履歴書への記載は変わります。
- 文部科学省管轄の場合:学歴欄へ記載
- 厚生労働省管轄の場合:職歴欄へ記載
資格取得のための民間スクールに関しても、通っていたスクールが学校教育法で定められた教育機関に該当するかどうかで判断します。
そのため、専門学校以外のスクールについては、学歴ではなく「資格欄」や「特技欄」「特記事項欄」に記載してアピールするのが一般的です。
履歴書の学歴は高校入学から書けばOK!書き方のルールを守って選考通過を目指そう
履歴書の学歴欄への記載は、高校入学から記載しておけば問題ありません。
とはいえ、学歴や職歴なども含め、応募先によって変動する場合もあります。
自身の思い込みなどで応募先企業に沿わない書き方をしてしまうと、選考時の印象を落としかねないため、応募企業先の記載ルールなどは必ず確認して正確に記載することが重要です。
また、履歴書の記載方法について不安な場合には、書類添削や相談に乗ってくれる転職エージェントの利用がおすすめです。
マイナビエージェントなら、書類の添削で正確な書類作成が叶ううえに、書類選考の通過率アップも期待できるため、転職が初めての方でも安心して利用できます。
\ 応募書類の添削サポートも手厚い!/





